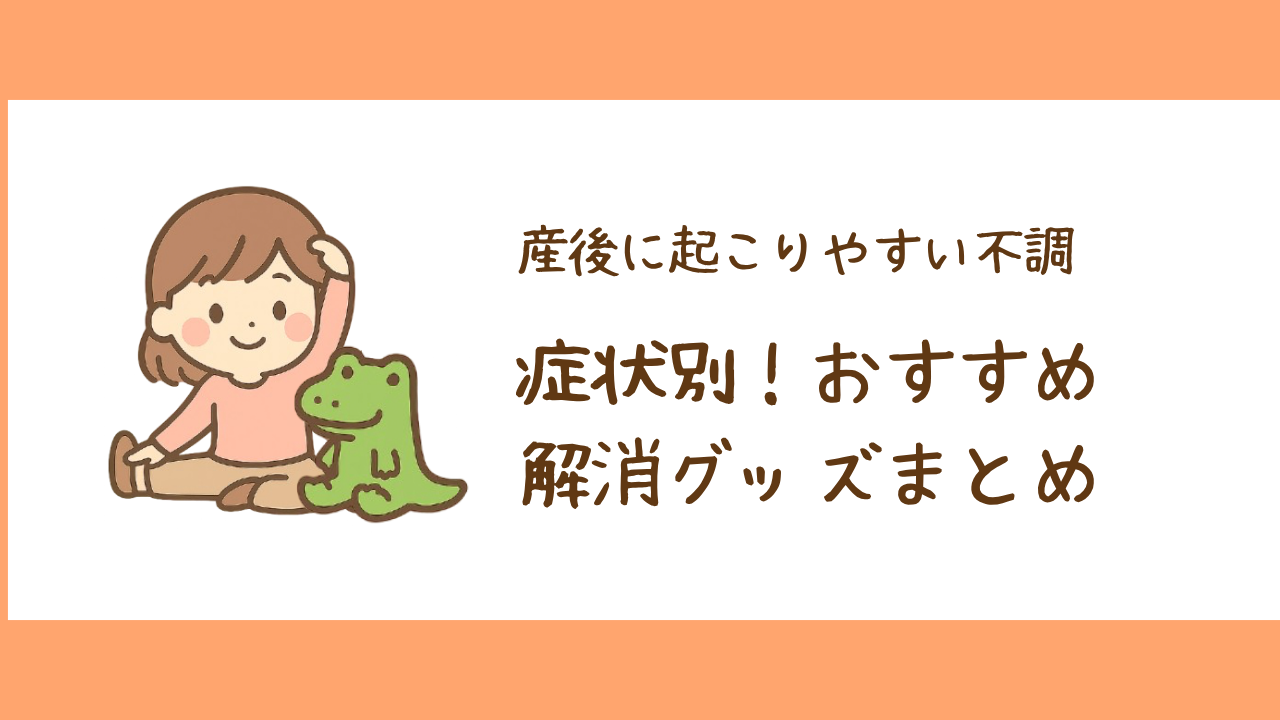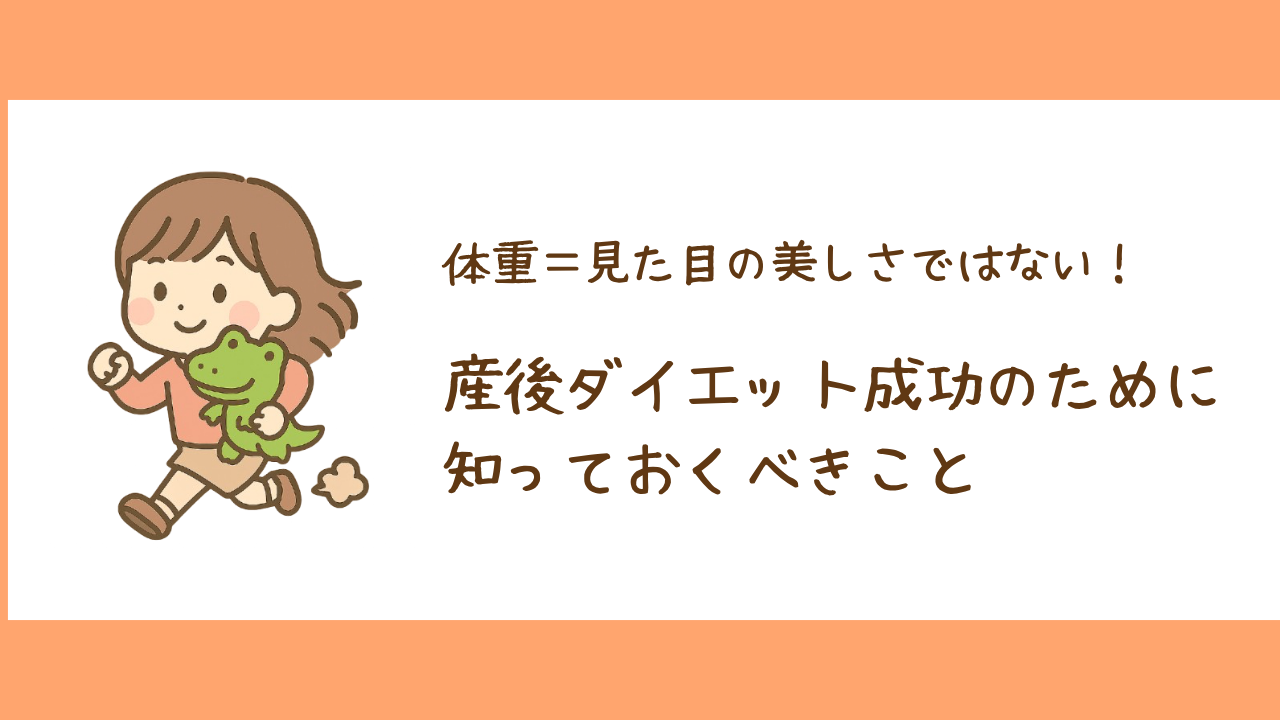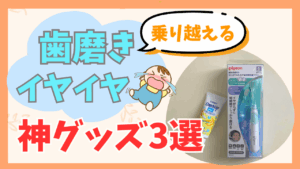赤ちゃんにテレビやYouTubeって、見せちゃダメなのかな?
「言葉の発達に悪い」「脳に影響がある」と聞く一方で、家事の合間やちょっとひと息つきたいときに、つい頼りたくなる存在ですよね。
うちも正直、毎日見せちゃってます。しかもけっこう長め…。見せるたびに「やっぱりよくないのかな」と罪悪感を抱きつつも、実際は歌に合わせて手を叩いたり、ダンスしたりと楽しそう。
「赤ちゃんにテレビやYouTubeを見せるのは本当にダメなの?」「見せすぎるとどんな影響があるの?」と疑問に思い、実際に調べてみました。
- 専門機関が示す“見せすぎNG”の理由
- わが家で決めた「テレビ・YouTubeOKライン」
- そしてテレビに頼りすぎないための代替アイテム(長く使えて、一人遊びに適しているもの)
を、実体験をまじえて紹介します。
赤ちゃんにテレビやYouTube、“見せすぎNG”な理由は?
赤ちゃんにテレビやYouTubeを長時間見せることについては、世界中の専門機関から「控えたほうがいい」という提言が出ています。
その理由は「脳や体の発達に影響する可能性があるから」。具体的に見てみましょう。
世界保健機関(WHO)のガイドライン(2019)
- 1歳未満の子どもには「まったく見せない」ことを推奨
- 2歳未満でもテレビやスマホなどの画面視聴は控えるべき
WHOが重視しているのは「運動・睡眠・人との関わり」の時間。
赤ちゃんにとっては画面よりも、遊びやコミュニケーションの体験のほうが脳の発達に良いとされています。
(出典:WHO『5歳未満の子どもに対する身体活動・座位行動・睡眠に関するガイドライン』2019年)
日本小児科医会の見解(2021)
- 2歳まではできるだけ見せない
- 2歳以降でも「1日1〜2時間以内」が目安
赤ちゃんに必要なのは、テレビよりも「人とのやりとり」。
会話や関わりの中でしか学べないことが多く、また次のような懸念も示されています。
- テレビは一方通行で、発語を促しにくい
- 睡眠の質の低下
- 集中力や視力への悪影響
(出典:日本小児科医会「子どもとメディア」委員会 提言 2021年)
アメリカ小児科学会(AAP)の提言(2016)
- 18ヶ月未満はビデオチャット以外の画面使用は避ける
- 18〜24ヶ月では「親が一緒に見て、言葉を添える」ことが条件
この背景には、2歳未満の脳はリアルなやりとりから学ぶことを前提に発達しているという考えがあります。
動画は「楽しいけど受け身」になりやすく、学習効果は薄いと指摘されています。
(出典:AAP『Media and Young Minds』2016年)
具体的にどんな影響があるの?
まとめると、赤ちゃんにテレビやYouTubeを見せすぎると、次のようなリスクがあるとされています。
- 脳への過剰な刺激
テンポの速い映像は情報量が多く、未発達な脳に負担をかける - 言葉の発達が遅れる可能性
一方通行の動画では「会話のキャッチボール」が育ちにくい - 身体への影響(運動・睡眠・視力など)
長時間座りっぱなしで運動不足/睡眠の質が下がる/視力に負担
赤ちゃんにとっては「遊ぶ・眠る・動く」といったシンプルな活動が何より大切。
画面時間が増えることで、その大事な時間が削られてしまうのが懸念されているのです。
各機関の提言をまとめると、次のような影響が指摘されています。

こうした理由から「赤ちゃんにテレビやYouTubeは見せすぎ注意」と言われます。
ただし「絶対にダメ」というより、どう見せるか・どんな関わり方をするかが重要なんですね。
YouTubeやテレビから“学んでいる”実感もある
正直、うちでは毎日YouTubeキッズや『おかあさんといっしょ』を見ています。
「見せすぎかな…」と反省することもありますが、実際に子どもの成長につながっていると感じる瞬間もあるんです。
- 動画の歌を口ずさむようになった
- 動きを真似して体を動かす
- 笑ったり驚いたり、表情が豊かになった
テレビやYouTubeも、子どもにとっては刺激のひとつ。
ママにとっても「ちょっと休憩できる時間」になって、結果的にイライラが減ることもあります。
だから私は、「完全にゼロにする」のではなく「バランスを取りながら付き合うもの」と考えるようになりました。
うちで決めた「動画との付き合い方」=OKライン
いろいろ試してみて、わが家では“無理なく続けられるルール”を決めました。完璧じゃなくても「これならやれる」と思える範囲にしておくのがポイントです。
- 時間を意識して区切る
目安は1回30分くらい。2〜3回見せる日があっても、「今日はこれで乗り切れた」と思えたらOKにしています。
- 内容は“子ども向け”で安心できるもの
YouTubeキッズの公式チャンネルや、『おかあさんといっしょ』『いないいないばあっ!』など教育番組を中心に。
- できる日は“声かけ”して一緒に見る
「おさかなさん泳いでるね〜」と少し声をかけるだけでも、ただの動画時間が“親子のコミュニケーション”になる気がします。もちろん、毎回一緒には無理なので「できるときだけ」で十分。
テレビ・YouTubeに頼りすぎないための“代替アイテム”4選
ここでは、「長く遊べる」×「一人でも遊べる」を軸に、おすすめアイテムを紹介します。
テレビやYouTubeに頼りたくないけど、今は一人で遊んでいてほしい…そんなときに活躍してくれるものです。
① ことば図鑑(タッチペンで音の出る絵本)
- 語彙力アップ:絵と一緒に言葉を覚えられるから自然と単語が増える
- 親子の会話が広がる:「これなに?」「○○だね!」とやりとりが増える
- 記憶力の発達:繰り返し読むことで定着しやすい



うちの子(1歳4か月)は、動物と色のページが特にお気に入り。
犬を見て「わんわん」、猫を見て「にゃー」と声に出したり、「青」「黄色」など色の名前も言えるようになりました。繰り返し読むたびに少しずつ言葉が増えていくのが嬉しいです。
② 楽器系(ピアノ・太鼓・木琴など)
- リズム感が育つ:音やテンポに合わせて体を動かす力がつく
- 表現力アップ:自分の気持ちを音で表せるようになる
- 手先の発達:たたく・押す・振る動作で指や手の動きが器用になる



音楽が流れると自然に体を動かして踊り出すのが定番。
鍵盤をポンポン叩いて音を鳴らすのも大好きで、ちょっとした即興演奏のように楽しんでいます。
③ ボールプール
- 全身運動になる:もぐる・投げる・拾うで自然に体を動かす
- 感覚遊び:ボールの柔らかさ・数・色の違いを体感できる
- ストレス発散:思いっきり動けて気持ちの切り替えに役立つ



最近はボール遊びに夢中で、ボール同士をカチカチぶつけたり、投げたりしています。
あちこちに飛んでいって片付けはちょっと大変ですが、楽しそうに遊んでいる姿に思わず笑ってしまいます。
④ おままごと系(キッチン・食材セットなど)
- 想像力が豊かになる:「料理を作る」「お店屋さん」などストーリーを考えやすい
- 社会性が育つ:親や友達と役割分担して遊べる
- 生活習慣の学び:「切る」「洗う」「盛り付ける」で実生活に興味を持つ



食材を切る遊びにハマっていて、「ザクッ」と切れるのが楽しいようです。まだ一人ではうまく切れないので横でお手伝いが必要ですが、本人はとても真剣。
最近はスプーンを持って食べる真似もしていて、ごっこ遊びの世界がどんどん広がっています。
完璧じゃなくていい。“子どもが楽しんでいる”ことを大切にしたい
ポイントを振り返ると…
- 見せすぎにはリスクがある
脳・言葉・体への影響が指摘されています - 内容や関わり方で“学び”にもなる
親子で声かけしたり、教育番組を選ぶことで受動的にならず楽しめる - 大事なのは「量」より「質」
見せたあとの関わり方や遊びへの切り替えがポイント - 代替アイテムで長く遊べる
知育おもちゃ・楽器・ボールプール・おままごとなど、年齢に合わせて成長できるアイテムはコスパ◎
育児は「これで正解」というものはありません。
動画を見せたことに罪悪感があっても、子どもを観察しながら考えて悩んでいる時点で十分。
私たちも子どもと一緒に少しずつ育児を覚えていく途中です。
だから今は、今のわが家に合った方法で、焦らず進めていけばいいと思います。