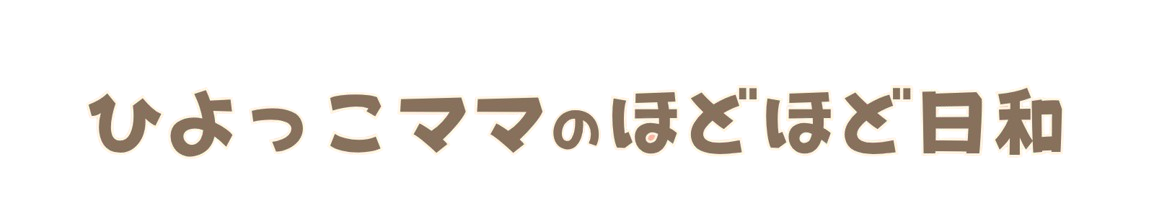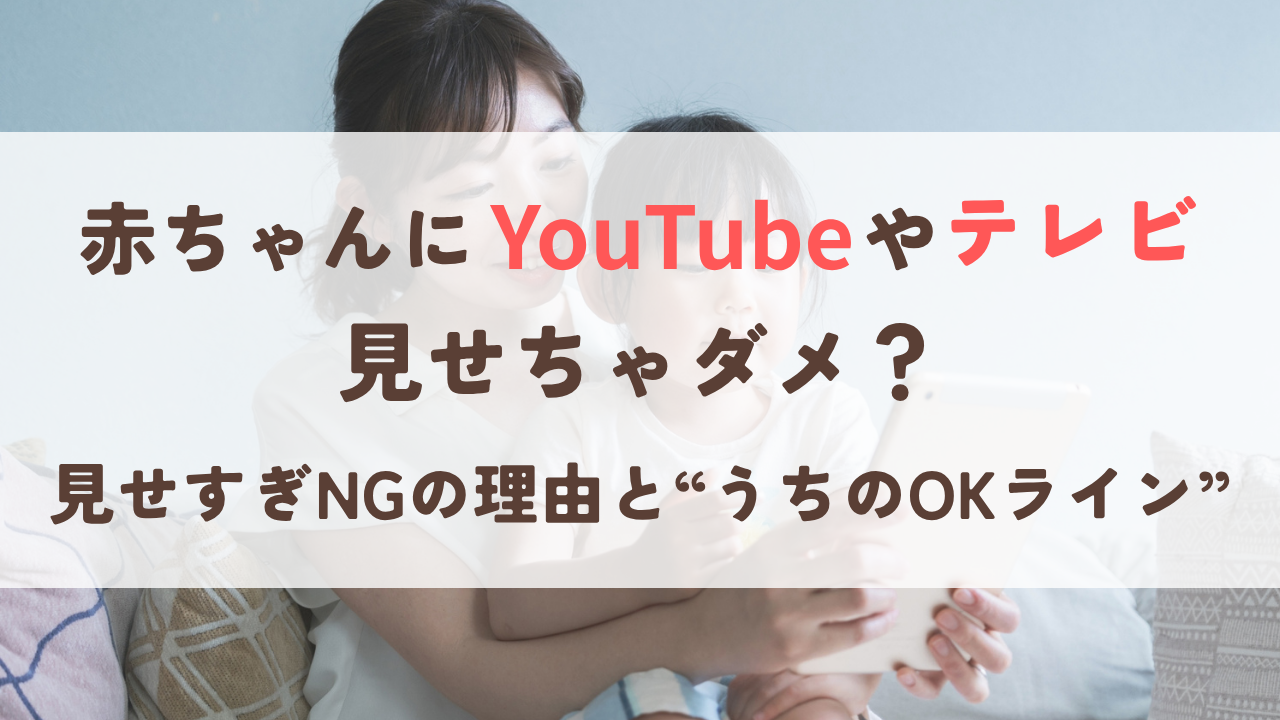赤ちゃんにテレビやYouTubeって、見せちゃダメなのかな?
家事の合間、ちょっとひと息つきたいとき。
静かにしててくれるなら…と、つい頼りたくなる存在。
でも、「言葉の発達が遅れるよ」とか「脳に悪いよ」なんて話もよく聞く。
うちも正直、毎日見せちゃってるし、しかもけっこう長め。
見せるたびにちょっと罪悪感もあって、でも実際は歌を聴いて、楽しそうに身振り手振りをしている。
「ダメ」って一括りにできるものなのかな?って、ふと疑問に思って調べてみました。
1|テレビやYouTube、やっぱり“見せすぎNG”な理由は?
赤ちゃんにテレビや動画を長時間見せることについては、世界中の専門機関から「控えめに」との提言が出されています。
その理由には、脳や身体の発達に関わる根拠があるんです。
1-1|世界保健機関(WHO)のガイドライン(2019)
- 1歳未満の子どもには「まったく見せないこと」を推奨
- 2歳未満には、テレビ・スマホ・タブレットなどの画面視聴は控えるべきとされています
その目的は、運動・睡眠・言語や社会性の発達を優先するため。
画面の前に座って過ごすよりも、「遊ぶ・人と関わる」といった体験の方が、赤ちゃんの脳の発達に良いという立場です。
出典:WHO『5歳未満の子どもに対する身体活動・座位行動・睡眠に関するガイドライン』(2019年)
1-2|日本小児科医会の見解(2021)
- 2歳まではテレビやビデオ視聴をできるだけ控えるべき
- 2歳以降でも「1日1〜2時間以内」が目安とされています
赤ちゃんにとって大事なのは、テレビよりも“人とのやりとり”。
言葉や感情の発達には、「会話」や「関わり」の中での学びが欠かせないと明言されています。
また、次のような懸念も指摘されています:
- テレビは一方通行で、子どもの発語を促しにくい
- 睡眠の質の低下
- 集中力や視力への悪影響
出典:日本小児科医会「子どもとメディア」委員会 提言(2021年)
1-3|アメリカ小児科学会(AAP)の提言(2016)
- 18ヶ月未満の子どもには、ビデオチャット以外の画面使用を避けるよう推奨
- 18〜24ヶ月の間は、「親が一緒に見て、言葉を添える」ことが前提条件とされています
2歳未満の脳は、リアルなやりとりから学ぶことを前提に発達しており、動画は「面白い」が先に立って、学習にはつながりにくいことも。
出典:American Academy of Pediatrics『Media and Young Minds』(2016年)
1-4|具体的にどんな影響があるの?
各機関の提言をまとめると、次のような影響が指摘されています。
脳への強い刺激
YouTubeなどの動画はテンポが早く、切り替えも激しいため、未発達な脳には処理しきれない情報量になることも。
光・音・動きが次々に押し寄せてくる環境は、知らず知らずのうちに脳に負担をかけてしまいます。
言葉の発達が遅れる可能性
赤ちゃんは、「リアルな会話のやりとり」の中で言葉を覚えていきます。
でも、動画は基本的に一方通行。
楽しい歌やセリフがあっても、「会話のキャッチボール」にはならないので、言葉を覚える力は育ちにくいという指摘があります。
身体への影響(運動・睡眠・視力など)
- 画面に集中しすぎて動く時間が減る
- 強い光の刺激や夜間の視聴で、睡眠の質が低下する
- 長時間近くの画面を見ることで、視力にも負担がかかる
とくに成長期の赤ちゃんにとっては、遊ぶ・眠る・動くといった基本的な活動が何より大切。
画面視聴の時間が増えることで、そうした時間が減ってしまうことが懸念されています。
このように、赤ちゃんの動画視聴には“見せすぎ注意”の理由がしっかりあることがわかります。
ただし、「絶対ダメ」というわけではなく、どう見せるか・どんな関わり方をするかが大事なんですね。
2|YouTubeやテレビから“学んでいる”実感もある
正直うちでは、毎日YouTubeキッズやテレビで『おかあさんといっしょ』を見せています。
そして、その中ではっきりと「成長してるな」と感じることもあるんです。
- 動画の歌を口ずさんでる
- 動きを真似して体を動かしてる
- 笑ったり、驚いたり、表情も豊かに
もちろん、ずーっと見せっぱなしだった日は「あ、今日はちょっと見せすぎたかも…」って反省することもあります。
でもそれは、私なりにその日を乗り切るために選んだ“手段”のひとつ。
子どもが笑って、私も少し笑えたなら、それも立派な一日だったんじゃないかな、って思います。
3|うちで決めた「動画との付き合い方」=“OKライン”はこれ
あれこれ悩んだ結果、今のわが家では無理せず守れる範囲でルールを決めました。
時間を意識して区切る(がんばらない程度に)
- 目安は1回30分まで
- 2〜3回見せる日があっても、心の余裕が持てたらOKにする
内容は“子ども向け”の安心できるものに
- YouTubeキッズ(公式コンテンツ中心)
- おかあさんといっしょ/いないいないばあっ!など教育番組
できる日は“声かけ”して一緒に見る
- 「おさかなさん泳いでるね〜」と少しでも声をかけてみる
- すべて一緒に見るのは無理なので、“できるときだけ”
4|“少し見せてるだけなのに否定される”…そんなときは
赤ちゃんに動画を見せてる、って話すと、
「うちは一切見せてないよ」「それってちょっと心配じゃない?」と返されることもあります。
もちろん、動画を見せない選択も、立派な育児のひとつ。
そうやって丁寧に向き合っている人も、たくさんいます。
でも、それぞれ家庭の状況や子どもの性格は違うもの。
一部分だけ見て、「これは良くてこれはダメ」と決めつけられるのは、やっぱりつらいですよね。
だから私は、こう思うようにしています。
「“どちらが正しいか”じゃなくて、“うちに合っているか”で選んでいい」
動画を見せる日もある。見せない日もある。
育児に“これだけが正解”なんてないからこそ、お互いの選択を尊重し合えたらいいなって思います。
5|完璧じゃなくていい。“子どもが楽しんでいる”ことを大切にしたい
- テレビや動画の“見せすぎ”にはリスクがある(脳・言葉・体への影響)
- でも、内容や関わり方によっては“学び”にもつながる
- 大事なのは「量」より「質」、“見せたあとの関わり方”
育児って、「これでいいのかな?」の連続。
動画を見せたことに罪悪感を感じる日もあるけれど、
それでもちゃんと我が子を見て、考えて、悩んでるなら、もうそれで十分だと思います。
私たちも子どもと一緒に、少しずつ育児を覚えていく途中。
動画の付き合い方だって、きっとこれからどんどん変わっていく。
だから今は、今のわが家に合ったやり方で、焦らずやっていこう。