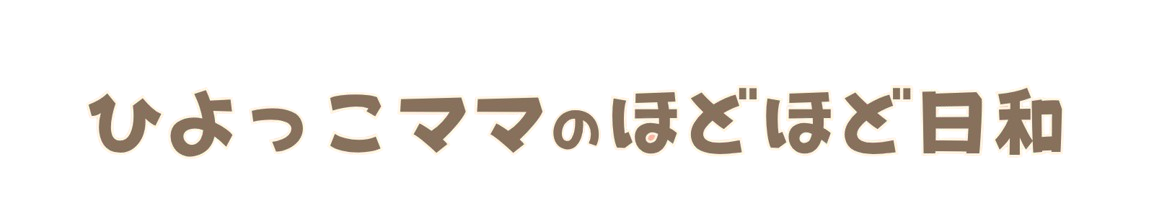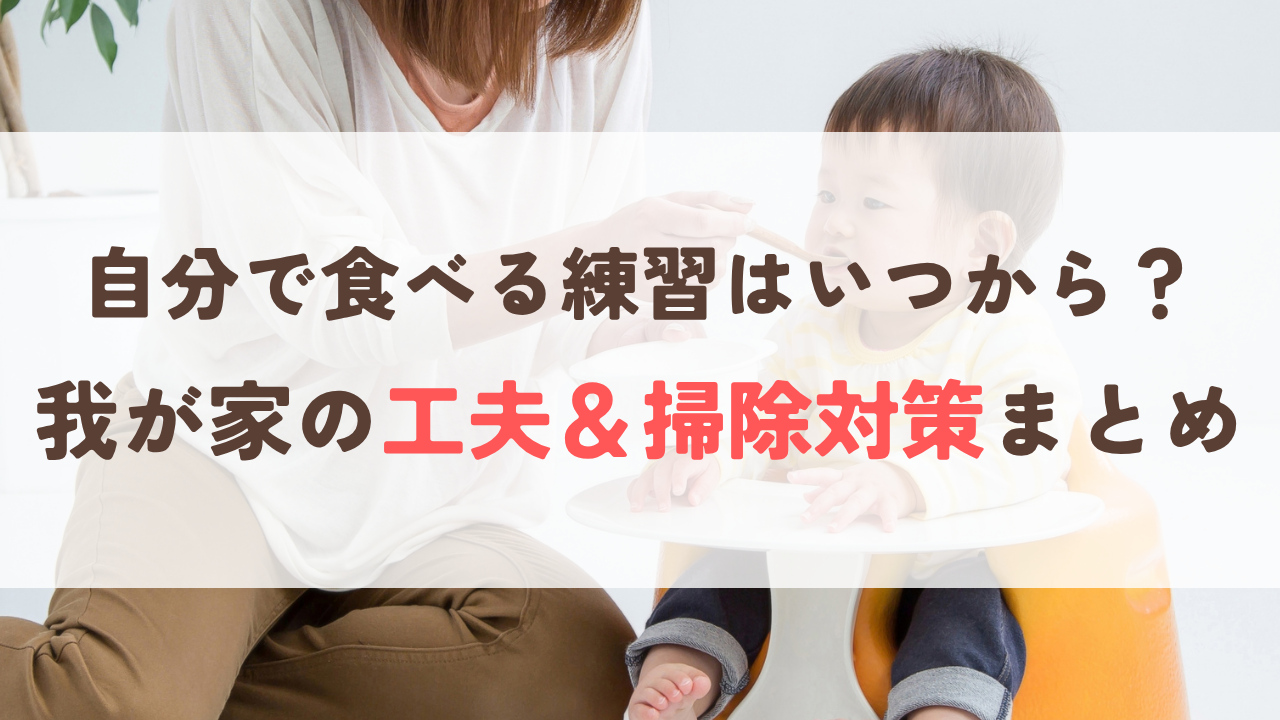1|自分で食べる練習はいつから?
1-1|わが子の場合
生後11ヶ月のある日。いつものように離乳食をあげていたら、突然、娘にスプーンを取られた!「えっ?」と思って見ていたら、空っぽの机に向かって、一生懸命すくう真似をしはじめてビックリ。
それまで“食べさせてもらうのが当たり前”って思っていたから、
「もしかして…そろそろ自分で食べたいサインかも?」って初めて気づいた瞬間だった。
試しにお皿ごと渡してみたら、ほとんどこぼしながらも意外と上手に食べていて、「すごーい!」と感動。
そこから、「自分で食べる練習、そろそろ始めてみようかな?」と考えるようになったよ。
1-2|一般的にはいつから練習させる?
調べてみると、生後9ヶ月〜1歳頃から自分で食べる練習を始めるのが一般的 らしい。
やらせてあげたい気持ちはあるけど、後片付けの手間がなぁ…というジレンマも。
やらせてあげたい気持ちはあるけど、後片付けの手間がなぁ…
そこで、いろいろ試行錯誤しながら実践してみた結果、1歳ごろには上手にスプーンが使えるようになった!
今回はママのストレスを極力減らせるスプーン食べの練習方法を紹介するね!
ちなみにスプーンはdoddl(ドートル)のスプーンを使用中!
私は楽天市場で購入しました♪
私は楽天市場で購入しました♪
つかみやすさ・すくいやすさ・食べやすさどれも満点で、わが子にはあってるみたい。
リンク
2|掃除の手間を減らす工夫
2-1|軟飯で練習
メリット
- 手でもスプーンでもすくいやすく、食べやすい
- パラパラこぼれにくく、ご飯のかたまりで拾いやすいので掃除がラク
デメリット
-
ご飯が机や椅子につくと、ちょっとベタベタする(でも拭けばすぐ取れる◎)
実際にやってみて
普通のご飯だとパラパラ落ちて掃除が大変だけど、軟飯だと固まりやすいから片付けが楽!
手掴みの練習にもなるし、スプーンの練習もスムーズにできるよ。
軟飯がついた机や椅子はベタベタになっちゃうので、ご飯後はおしりふきでサッと拭いてるよ!
手掴みの練習にもなるし、スプーンの練習もスムーズにできるよ。
軟飯がついた机や椅子はベタベタになっちゃうので、ご飯後はおしりふきでサッと拭いてるよ!
2-2|机にくっつくお皿の活用
私は楽天市場でこちらを購入しました。
リンク
メリット
- すくいやすい形で設計されていて、子どもが取りやすい
- 強力な吸盤で机に固定できるから、ひっくり返される心配がない
デメリット
- 吸盤がくっつきにくい素材があるから事前にチェックが必要
実際にやってみて
私はノウスのハイチェアに使用中。
木製の机よりも吸着力は劣るけど、特に問題なく吸着してくれます。
木製の机よりも吸着力は劣るけど、特に問題なく吸着してくれます。
お皿をひっくり返したり、振り回されることがないから快適です!
お皿が滑らないから子どもはスプーンですくいやすそう!
お皿が滑らないから子どもはスプーンですくいやすそう!
いつか自力ではがされる時が来るまで、このお皿は現役です(^^)
2-3|机まで覆えるお食事エプロン
私は楽天市場でこちらを購入しました。
リンク
メリット
- 机、服、椅子への汚れをほぼ防いでくれる
- 食べこぼしが全部エプロンの上に落ちるので掃除が楽
デメリット
- エプロンの着脱が手間
- サイズが大きくて洗うのが大変
- 複数枚買うとなるとコストもそこそこかかる
実際にやってみて
実際使ってみたら、確かに汚れは減ったけど、エプロンの着脱が地味にストレスで、サイズが大きいから洗うのも一苦労。
めんどくさがりの私には続けるには手間だと感じたので、今はシンプルなエプロンで落ち着いてる。
どうしても汚してほしくない!って思ってるママには一番おすすめだよ!
2-4|食べこぼしシート(ダイソーのマスカーフィルムを使用)
メリット
- 机や床の汚れを気にせず、思い切って食べさせられる
デメリット
- 毎回取り替える手間がある
- 消耗品なのでコストがかかる
実際にやってみて
めんどくさがりな私には毎回シートを敷いて片付けるのが思った以上に面倒…。
結局、拭き掃除の方が楽だなってなって、今は使ってない。
結局、拭き掃除の方が楽だなってなって、今は使ってない。
何でもポイポイする時期が来たら、もう一度使い始める予定!
3|私のおすすめの組み合わせ
色々試してみた結果、今のところ私が落ち着いたのは軟飯+机にくっつくお皿 のシンプルな組み合わせ。
軟飯なら手掴みもしやすいし、床や椅子についても掃除がラク。
机にくっつくお皿を使うことで、ひっくり返されるストレスもなくなった。
机にくっつくお皿を使うことで、
「机まで覆えるお食事エプロン」や「床に汚れ防止シート」も試したけど、手間やコストを考えると我が家には合わなかった。
シンプルだけど、これが一番無理なく続けられてるよ!
4|まとめ
子どもが自分で食べる練習をする時期は生後9ヶ月〜1歳頃が目安。
その時期に合わせて掃除の手間を減らす工夫をすることで、ママも楽になる!
その時期に合わせて掃除の手間を減らす工夫をすることで、
我が家では「軟飯」と「机にくっつくお皿」の組み合わせがベストだったけど、他にもいろんなアイデアがあるはず。
無理なく楽しく、子どもが自分で食べられるようになるまで見守っていこう!